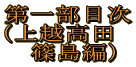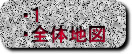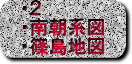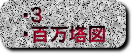翌日、顕信と篠島の神職二見貞友が中心となり,島の主要な者達を集め今後の方策について何回かの話し合いをもった。とにかく如何にしてこの島から吉野にまで戻るか。ただなかなか結論を出すには至らず、また若い顕信には議題を制御することはできず話は様々な方向に逸脱した。その脱線を通じて顕信は自分の考えと神職二見の考えに合致する点がままあることに気が付いた。実は、暫くたってからではあるが顕信と二見には共通の思想的基盤があることが分かった。
二人とも伊勢神宮の外宮の禰宜(ねぎ)度会家行(わたらいいえゆき)と言う人物に一時期、時間的な相違はあるが、師事していた。実は顕信の父北畠親房もこの度会に師事しているのだ。
思想的根底から言えば朱子学であり、主張する政治理念の実現にむけては軍事的行動をも辞さないあるいは実際に軍事行動を実施するという実践思想である。北畠家ももともと朱子学派であった上に、度会家行の思想的影響もあり天皇親政実現のためにこうして粉骨砕身、公卿という最高位の貴族でありながら、武家以上に武家的な日々を送ることになったのである。
神職も島長の篠島太夫もまた目西も、夕食の際、親王に合わせて天水の変わりに酒を飲んだ。そして酒を飲んだ上で会議に臨む。酔いもあるのであろう。会議ではつい皆口が軽くなる。神職が最近の政治的動向について喋り始めた。神職は年に最低三度はおんべ鯛で伊勢に行く。その際に様々な政治的情報を入手するが、伊勢神宮という場所からして、特に皇室を中心とした動向を把握できるのである。ただし、同時性には常に欠けるが。今は丁度十月の神嘗祭(かんなめさい)の前にあたり情報の最も欠如した時期にあたっている。前回の情報は六月の月次祭。その時点では、顕信が義良親王を奉じての東国平定の勅命を受け、伊勢の大湊から海路東国へ出航するという重要情報は手にしていない。神職の持っていた最新情報と言えば、眼前にいる顕信の兄、北畠顕家が五月に高師直と堺の石津で戦い敗死してしまったことぐらいである。もちろん閏七月の情報はない。その後の重要な動きを、逆に顕信に訪ねた。そこで顕信はこの閏七月初旬に左中将義貞殿が越前の灯明寺畷(とうみょうじなわて)にて細川出羽守孝基の歩射部隊に遭遇し不意打ちを受けついに自害し果てたという話をした。
この話を聞いて突然無口のはずの目西が口にしてはならぬことを言った。
「吉野帝のお味方総崩れ」
一同、一言も反応することはできず。まずもって帝の前に吉野という地名が冠されたことが問題である。これではまるで京にも別の帝がいるということを肯定してしまう。また、確かに、目西自身しばらく忍びとして同道していたことのある楠木正成をはじめ南朝方の主たる武将達はことごとく散り果てようとしている。目西が総崩れと言ったこともあながち否定できないのだが、これを露骨に口にするとは。
宵の口、かなりの時間、誰も口を聞かず虫の音と潮騒だけが聞こえていた。目じりの下がった島長がなさけなげな声で言った。
「目西、不謹慎なことを申すでない。こやつの頭はいかれておる故、皆のものご無礼つかまつったの。許されたし。」
神職もこの場の雰囲気を変えようと思い話を始めた。
「伊勢で禰宜達ではなく巫女達と話すと宮中の色恋沙汰やろくでもない噂話が多くて、でもそれが実は愉快で面白い。思い起こせば新田左中将義貞殿の一大恋愛事件も聞いたことがある。」
神職は冗談も織り交ぜながら皆に向けて語り始めた。
左中将義貞の御相手とは彼の奥方である勾当内侍(こうとうのないじ)。
この女性、頭大夫藤原行房の娘で、美殿の奥深く絢爛たる帳のかげにあでやかな美貌を育まれた。十六歳の春に内侍に召され帝の御側に仕えたが、薄絹にもたえないその艶姿はあたかも春風が一片の花びらを吹き残したかと疑われ、華やかに粧われた顔は、秋の雲間の月が川面の水を照らすかと思われた。過ぎにし建武初年(1334)左中将は内裏の御警護に当たっておられた。そんなある夜、勾当内侍は御簾を半ば巻き上げ琴を弾いておられた。中将はその調べに心惹かれ、御所を彷徨い竹垣から勾当内侍の様子を覗った。中将は有明の月の下、たおやかになまめく勾当内侍に強く心を奪われてしまった。中将は宮中から帰宅しても内侍の面影がなおも眼前にあり心を迷わし万事がうわの空と化してしまった。
そこで
わが袖の泪に宿るかげとだに
しらで雲井の月やすむらん
左中将はこの歌を勾当内侍に届けた。しかし内侍は帝の御耳に入ることを恐れこの歌を受け取らなかったという。中将の落胆振りたるや。<太平記現代語訳>
ところが誰が奏上したのか、いつしか帝も左中将の一途な恋を哀れなことと御思いになられた。御遊宴のおりに左中将を召されて御酒を賜ったとき、帝は
「勾当内侍をこの盃に添えて」
と仰せになった。左中将は喜びいさんで翌晩さっそく牛車を美しく仕立てて内侍をお迎えに行った。内侍も彼の心を知り誘う水あれば行こうと思い定めていた。
<太平記現代語訳>
かくして左中将と勾当内侍は結ばれたという。
「その左中将殿も自害し、その首は都大路を引き回されて獄門にかけられたとは。さぞや勾当内侍は辛く悲しかろうて」
島長が顕信に向けて呟いた。一方、顕信は神職の話を聞くにつれ、自分の父親北畠親房が語った親房自身と中宮禧子の身の上に起こった恋愛沙汰を思い出し、話を重ね合わせて非常に複雑な心境であった。ましてその申し子が眼前にいるのである。
再び座が静まり返った。東国平定で出陣しながら御座船そのものが難破している。他の船が今どこでどうしているのか。今はなにも分からない。そしてまたどうやって島から帰還すれば良いのか。しかしそれは明日になれば、尾張に調達に出ている島人から何らかの情報がもたらされる可能性はある。その時の情報によりけりではあるが、それまでこの沈んだ雰囲気は変わらないのかもしれない。島人は元来無関係なのだが、根底にあるのは日ごとに勢力を増す足利北朝方、逆に年毎に有力武将を失いまた日ごとに勢力を落とす後醍醐帝側。顕信にとっては切実な問題である。ことの始まりは後醍醐帝そのものにあると人は言う。不公平な論功行賞、不公平な裁き、不慣れな武門の統率。なにをとっても建武政権の運営、管理、実務には確かに問題が多い。顕信の兄顕家が死の直前の高師直との戦のさなかに帝にその多くを諫言奏上しているが。しかし、そもそも建武親政を始めたとき、北畠家より本当の意味において武門の筆頭である清和源氏が始祖の足利家が支援すべきだったのではないのか。建武二年(1335)中先代の乱のおり、帝が足利冶部卿高氏に彼の願いに応じて征夷大将軍と総追捕使に彼を任命していれば。あるいは彼が建武政権の中枢に加わり政権は安定していたのかもしれない。彼の官位剥奪とは逆にもし足利を公卿に取り立てのぞみ通り征夷大将軍の官位を授ければ、傀儡天皇を基に幕府を開き実権をにぎるという野望をすて後醍醐帝を支援し得たかもしれない。ただあくまでも実権は天皇に集中する必要があるが。しかし、それはどの道、後醍醐帝には絶え難いことなのかもしれない。顕信はあるいは、この中先代の乱のおりに鎌倉二階堂の土牢で乱中のどさくさで処刑されてしまった兵部卿護良(もりよし)親王の気風であれば建武政権を安定に導けると思うこともあった。ただもともと、足利冶部卿高氏と兵部卿親王は互いに上手くいかない宿命。冶部卿は周到かつ政治力にたけ武門の棟梁、一方、兵部卿は質実剛健でありかつ天台座主という仏門の棟梁。御互いを補間し合える関係でもあり、相容れない関係でもある。兵部卿親王に悪風がたち結果的に冶部卿がそれを上手く政治的に利用し兵部卿を滅亡させてしまったが。顕信はこの時点こそが建武政権の凋落の始まりと考えている。
それと同じような考えをこの孤島の神職二見が話したのには正直顕信も驚愕した。こおろぎの音を破り神職二見が語った。
「左中将義貞公の喪失は後醍醐帝にとってさぞ大きなる痛手。先だっての顕信将軍殿の兄君顕家殿、また先年の楠判官正成殿の死、そしてなによりの発端は大塔宮の処刑からでございましょうや。これもまた、外宮の巫女が噂にしていた話でございまする
が」
と前置きし、兵部卿護良親王すなわち大塔宮(おおとうのみや)の悲劇について語り始めた。
建武元年(1334)。その時までには高氏卿と大塔宮の間にはすでに幾重にも積もった憎しみがあったという。大塔宮は高氏卿を討とうと思っていたが帝のお許しが無く自制して折られた。が時がたち、ついに内々の謀議のうえ諸国へ命じて兵を集められた。
高氏卿はこのことを聞き及び、密かに大塔の宮の継母にあたる三位局康子(れんし)を通じて帝に奏聞された。
「兵部卿親王は帝位を奪い奉るために、諸国の兵を集めておられます。」
そして、諸国へ発せられた宮の令旨を奪い取ってご覧に入れたので帝は酷く御怒りなり、
「この宮を流刑に処せ」<太平記現代語訳>
 かくして大塔宮は三位局康子(れんし)の讒言により鎌倉二階堂の土牢に閉じ込められてしまった。宮は南の御方という上臈ひとりのほか付き添う者も無く日月の光も見えない牢の中で、横殴りに吹き込む雨に御袖を濡らし岩間からの滴りに御枕も乾かぬままに、一年の半分以上も過ごされた御心の内を思いやるこそ悲しかった。
かくして大塔宮は三位局康子(れんし)の讒言により鎌倉二階堂の土牢に閉じ込められてしまった。宮は南の御方という上臈ひとりのほか付き添う者も無く日月の光も見えない牢の中で、横殴りに吹き込む雨に御袖を濡らし岩間からの滴りに御枕も乾かぬままに、一年の半分以上も過ごされた御心の内を思いやるこそ悲しかった。
<太平記現代語訳>
神職はここまで語って目西以上に言ってはならぬ大変なことを口ずさんだことにやっと気が付いた。阿野廉子がその心を砕いて止まぬ溺愛する実子の親王こそ、只今現在この篠島を御座所とする義良親王なのだから。
場の気詰まりの雰囲気は如何ともし難かった。虫の音と潮騒を目西の声が打ち
破った。
「水は高きから低きに流れる。たとえ土中でも。たとえ孤島でも高きと低きがあらば」だれも目西の言葉の真意を捉えられなかった。この場のいたたまれなさに島長がまとめに入った。
「ささ、今宵も更けてまいった。皆のもの解散としようぞ」
Copyright(c) 2019. Gigagulin (偽我愚林)