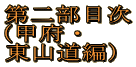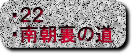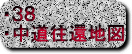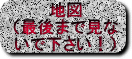真里は甲府から高尾行きの中央線普通に乗った。しばらくして笹子トンネルを越えると山梨県でも郡内と呼ばれる地域に入る。比較的広々として遠景に南アルプス、鳳凰三山や秩父、八ヶ岳など名だたる山々を見る甲府盆地とは異なり、郡内は接近した山と山に挟まれた谷筋の土地及び背景に巨大な富士を頂く富士五湖地域から成る。
大月駅で次の河口湖行きの富士急行線普通が発車するまで30分以上待ち時間があった。単線のローカル私鉄なのだから仕方がない。待ち時間が長いのは当然である。真里はホームにある「吉田のうどん」と言うのぼりの出ているうどん屋に入ってやや遅めの昼食を摂ることにした。腰の強いうどんで、具にキャベツが入っているのがめずらしい。さらに七味の代わりに護摩油で練ったからしを使うのもこの地域独特である。本来、大月ではなく富士吉田の名物なのだが。名物といっても「ほうとう」ほど世に知られているわけではない。が実は、ほうとうが普段食に対して吉田のうどんはハレの席でのご馳走なのである。真里は時々ではあるが学生時代に食べていた。ただこの大月駅の店はカレー屋も兼ねたお店で本格的な吉田のうどんではない。店はホーム側つまり改札内からの客と駅外つまり改札外からの客が双方側から入れるため、店内に境界が設けられている。真里が店に入った時ホーム側のテーブルには誰もいなかったが、境界の向こう側には数人サラリーマン風の客がいた。皆、コートを着たままカレーやうどんを食べている。セルフサービスなので真里は自分で水をコップに汲み、出されたうどんを自分でテーブルまで運んで食べた。食べ終わってから時計を見たが未だ15分以上待ち時間が残っていた。この店は幸い禁煙ではない。やや気が引けるものの真里はタバコを吸った。案の定、サラリーマン達の視線を感じた。
三月下旬の曇り。寒い日であった。大月からの河口湖行き普通電車はひたすらに標高を上げる。それとともに気温は徐々に低くなっていく。大月から富士吉田までのこの路線は単調に高さを増し決して下ることがない。大月から少し行くと富士吉田までは、桂川(相模川)、中央高速河口湖線、国道139号線と富士急行線が、時にお互いクロスすることはあるが、消して1キロ以上離れることなくほぼ平行して延々と続いていく。この間、人里が途切れることなく線上に続いていく。
大月と都留の中間点あたり。禾生(かせい)駅を過ぎた当たりからか、雪が降ってきた。この辺りからは田畑や建物の北面で日の当たらない場所に所々ではあるが雪が残っている。実のところ東京からは100kmと離れていないにもかかわらず、こんなに寒い場所があることはあまり知られていない。冬は甲府より3℃は低い。東京都心で桜が散るこの頃、甲府では梅が咲き終わろうとしている。でもここでは、梅は未だ満開だ。
都留にある大学の最寄り駅までで、真里の記憶では二回、桂川をこの電車は横切る。大月から約30分で目的地に着く。目的地に近づくに当たって婚約者だった助教の清水との記憶が蘇ってくる。つい数年前まで傷は癒えているはずなのにも関わらずここに来ることができなかった。線路脇の公園、駅前のスーパー、ファーストフード店、大学の図書館。思いでは尽きない。都留を再び訪れることができたのはたかだか一昨年のこと。郡内の公立図書館との交流事業で来ざるを得なかったためである。結婚でもしていればここを訪れることに関し心にゆとりがあろうものを。しかし真里は未だ独身である。清水のこと自体がどうのこうのというのではないが、彼のせいで婚期を逃したのではと言う忸怩たる思いを今も感じているのである。焦燥感がないと言えば嘘になる。この地にくると真里ははっきりとそれを悟らされた。
真里は先ず大学の総務課を尋ねてみた。そこで職員に単刀直入に砂博士こと高森准教授は今どこで何をしているかを尋ねた。「今この大学にはおりません」それ以上は個人情報なのでお答えできないとの返答。至極当然の答えである。総務課を尋ねた自分が馬鹿であったと思った。でも記録は必ずある筈。大学の教授職と言うのは一種の公職であって、どのような研究に従事しているのかは公開が原則ではないかと真里は思った。であれば、やはり図書館に行くのが早い。
久しぶりのキャンパスである。春休みのため人気はほとんどない。昔取った杵柄とでも言うのか、半ば本能的に本部棟の西にある図書館に真里は急ぎ足で向かった。雪が髪に付くのが嫌なのでかなりの勢いで走った。図書館に着いた時には肩で息をしていた。2階がエントランスとなっていて、ホールに入る手前で服と髪や肩に付いた雪を払いそれから中に入った。エントランスホールはオープンスペースと言われインターネットの使える端末が多数並んでいる。春休みでも利用者はいるようである。その内何台かは学生ではない人に利用されていた。と言うのもこの大学付属図書館は学外の市民にも開放されているパブリックライブラリーだからである。
まず、自分で探しても教職員の記録など見つけられる分けはない。司書である真里は直感で分かった。この図書館の司書に尋ねるのが早い筈。場合によっては自分の先輩か後輩が司書をしているかもしれないと思った。と、案の定である。カウンターにいる司書、見覚えがある気がした。確か後輩の筈。ただ、学生時代、しゃべったこともなければ名前も知らない。でも間違いなく学部の後輩である。普通の子であればしゃべったこともない後輩など忘却の彼方であるのだが。学生時代と変わらぬ独特の瓶底眼鏡で彼女であると認識できる。
真里が4年生になった頃。清水と学内で散歩デートしていたとき瓶底眼鏡をかけた新入生らしき子が、二人の前にある自動販売器でペットボトルのミネラルウォーターを買っていた。グレーで無地のフリースを着て、肩から大きなトートバックを提げていた。その眼鏡の瓶底度があまりにもすごくて清水と影で笑ったのだ。その新入生はボトルを肩から提げた駅前のスーパーのロゴ入りトートバックにしまい、それから徐にポケットからくちゃくちゃのハンカチを取り出して、瓶底眼鏡を外してレンズをそのハンカチで拭いた。眼鏡を外した瞬間、清水も真里も唖然。これがどうして、その身なりからは想像し難いのだが、綺麗なのである。多分メイクは何もしていないであろう。よくよく見ればスマートでしかも美しい顔立ち。眼鏡をコンタクトにして多少メイクをして、多少持ち物や服装を変えればものすごく目立つ子になるだろうに。そしてミスキャンパスも確実だろう。でも少なくとも真里が卒業するまでは、果たせるかな瓶底眼鏡はもとよりトートバックまでもがその子のトレードマークのままで
あった。
それから、何年たったのだろうか。未だにトレードマークの瓶底眼鏡を着用している。多少フレームは真里の記憶と違うようであるが、大体同じような感じだ。だからこそ彼女と認識できる。でも、昔と異なってメイクは少ししているようである。一昨年にこの図書館に交流事業で訪れたときには彼女はいなかった筈である。
「すみません」と真里はカウンター越しに声を掛けた。そして彼女に、過去に在籍した教職員のその後の行き先が分かるか尋ねた。
「調べれば分かると思いますが。そこの検索依頼と書かれたフォームに必要事項を書き込んで下さい」
眼鏡の印象とは裏腹な気弱そうな声だった。
真里は必要事項を書き込み、その用紙を渡した。その司書が用紙を受け取る時、真里は薬指に指輪をしているのに気がついた。左手である。当然よね、これだけの子だもの。と同時にもったいないのねと真里は思った。
「十年程前、自然科学系で准教授をしていた先生なんですけど」
「暫くお待ちください」
来館者が少ないためか、結構親切で直ぐに真里の検索依頼に応じてくれた。司書はカウンター内にあるキーボードで情報を入力した。暫くして、瓶底眼鏡を通しても眉を顰めて考え込んでいる様子がわかった。
「申し訳ございません。データが見当たらないようです。総務課の方にお問い合わせしていただいたほうが」
「ここに来る前に総務課で尋ねてみたのだけど、やっぱり分かりませんって
言われたわ」
「そうですか。すみません」
「いえ、気にしないで。大したことじゃないんで。どうも有難う」
そう言いつつ真里は溜息を漏らした。駄目か。分からないか。そう思いながら諦めてエントランスホールの出口まで歩いた。そこで真里はもう一度、カウンターに司書がいるか振り返った。忘れ物でもしたかのように真里はカウンターに引き返し、その司書に声を再びかけた。
「ねえ。あなた。ここの卒業生でしょ。実は私、在学中にあなたをお見かけしたことがあって覚えているのよ」
「えっええ。一応卒業生です」
「私も実は卒業してから図書館で司書をしているの。三杉真里。よろしくね」
と言って真里は自分の名刺を彼女に差し出した。彼女は受け取った名刺をしばし眺めた後、机の下に隠れていたトートバックから名刺入れを探し出し、そこから真里に名刺を渡した。
「畠山アリスと申します。よろしくお願いします」
「先輩、後輩というか、同業者のよしみというか、もし覚えていたら教えて欲しいのだけれど、ほら、自然科学系の授業で髭づらの先生いたでしょ。私は砂博士って呼んでたんだけど。覚えてない」
「覚えてます。あっ、さっきの検索依頼の高森先生って、もしかしてあの砂博士のことだったでんすね。苗字だけだったので」
畠山は懐かしい話で少し緊張感が取れたようであった。
「そう。あの高森よ。あの先生って今どこで何しているのか知らない」
「そう言えば確か私が在学中、筑波の何とかと言う研究所にご栄転されたとかと言う話を聞いた覚えがあります」
「どこの研究所かしら。今もそこにいるのかしら」
「それは分かりませんが。ネットでちょっと調べて見ましょうか」
そう言うかいなか、畠山はまた端末に向かった。そして暫くして瓶底の奥の眼を
輝かせ
「ありました」
と比較的大きな声で真里に言った。
「独立行政法人**総合研の教授のようですね。今、そちらの端末で見てみ
ましょう」
そう言って畠山はカウンターを出て、真里とともに空いているオープンスペースの端末に向かった。そしてサーチエンジンに幾つかのキーワードを入力し**総研の高森教授のページを開いた。
「本当だ。相変わらずね。この研究室の写真ていったら砂ばかりね」
畠山と真里は微笑んだ。
「出力しておきますか。このページ」
「ええ、お願いするわ。親切にありがとう」
畠山はカウンター内に戻り、カウンター内のプリンターからページを出力し、それを真里に渡した。
「今日は本当に有難う。またそのうち逢いましょ」
「どういたしまして。ではまた」
真里は充実した気持ちで図書館を出て雪の中そのまま駅に向かった。もう日が暮れてきていた。駅に大月行きの列車が入線しているのが見えた。真里は走った。学生の頃と同じように。そしてぎりぎりで列車に飛び乗る。
ドアが閉まり電車が動き始めても、暫く真里ははあはあと息を切らしていた。心の中は今日の図書館での出来事と筑波**総研の発見でいっぱいで過去の思い出の入る隙間はなかった。
大月駅での待ち合わせ時間に真里は携帯で**博物館の代表に電話を架けた。東ではなく野本が出た。東ではなく野本であったことに真里は安堵した。砂博士こと高森先生が現在は筑波にある独立行政法人**総合研究所の地圏**研究部門で主任研究員をしていることを事務的に伝えた。野本は礼をひとしきり述べた後、東に明朝伝えると言って電話を切った。野本は実直な好青年だなと真里は感じた。それとともに野本の綺麗な目を思い出した。
かつて毎日通学で見慣れた真里ではあったが、笹子トンネルを越えた中央線からの甲府盆地の澄んだ夜景はとても綺麗だと感じた。
Copyright(c) 2019. Gigagulin (偽我愚林)